Webサイトの回遊率を上げる方法とは?効果的な8つの施策と内部リンク最適化を解説
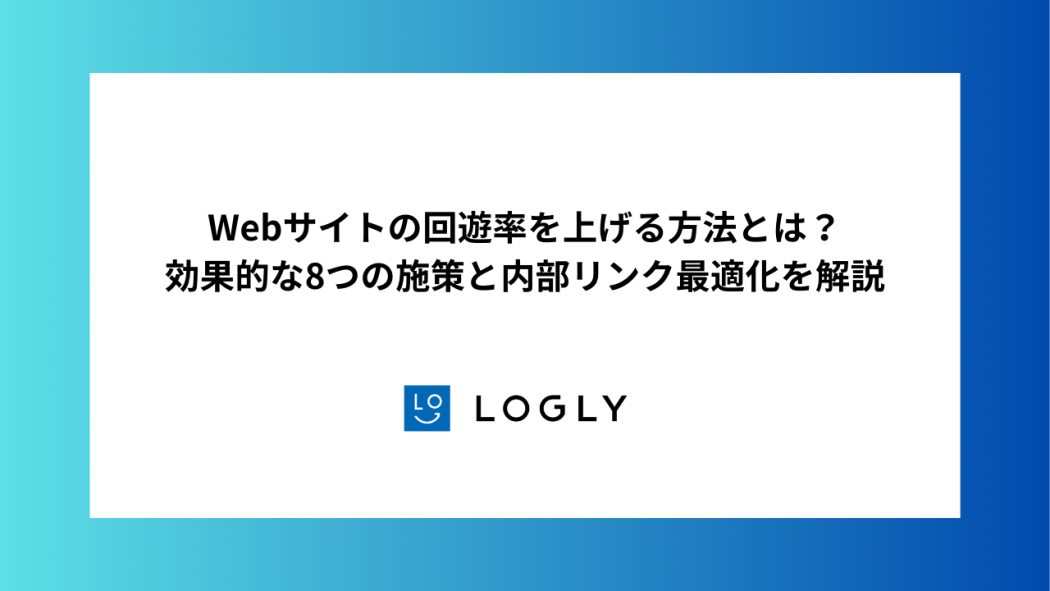
「自社サイト、アクセスはあるのに直帰率が高い…」
「ユーザーにもっとサイト内の色々なページを見てほしいけれど、どうすればいいんだろう?」
「Webサイトの回遊率を上げるには、どんな施策が効果的なの?」
Webサイトを運営していると、このような悩みに直面することがありますよね。せっかく集客したユーザーが、1ページ見ただけですぐに離脱してしまうのは非常にもったいないことです。ユーザーにサイト内を巡ってもらい、より多くの情報に触れてもらう「サイト内回遊」を促すことは、Webサイトの成果を高める上で非常に重要になります。
この記事では、Webサイトの回遊率の基本から、回遊率が低い原因、そして具体的な改善施策、特に重要な「内部リンクの最適化」などについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
この記事を読めば、自社サイトの課題を発見し、回遊率を高めてユーザー満足度とコンバージョン向上につなげるための具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
目次
そもそも「回遊率」とは?【重要性と目安を理解する】
回遊率の定義:1訪問あたりの平均PV数
回遊率とは、一般的に「1訪問(セッション)あたりに、ユーザーが平均して何ページ閲覧したか」を示す指標です。平均ページビュー数(ページ/セッション)として、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールで確認できます。
例えば、あるユーザーがサイトを訪問し、Aページ→Bページ→Cページと閲覧して離脱した場合、この訪問でのページビュー(PV)数は3です。サイト全体の訪問における、この「1訪問あたりの平均PV数」が回遊率の基本的な考え方となります。
計算式:
回遊率(ページ/セッション) = サイト全体の合計PV数 ÷ サイト全体の合計セッション数
回遊率が高いほど、ユーザーはサイト内で多くのページを積極的に見て回っている、ということになります。
なぜ回遊率が重要なのか?
では、なぜ回遊率を高めることが重要なのでしょうか?主な理由は以下の通りです。
滞在時間の向上: 多くのページを見るということは、それだけサイトでの滞在時間が長くなる傾向があります。
エンゲージメントの向上: サイト内の様々な情報に触れることで、ユーザーの商品やサービス、ブランドに対する理解や関心(エンゲージメント)が深まります。
SEOへの間接的影響: 回遊率や滞在時間の向上は、ユーザーがサイトに価値を感じている証拠と見なされ、検索エンジンからの評価(SEO)にも間接的に良い影響を与える可能性があります。(ただし、回遊率自体が直接的なランキング要因ではありません)
コンバージョン機会の増加: サイト内を巡る中で、ユーザーが購入や問い合わせといったコンバージョン(成果)に至る機会が増えます。様々な角度から情報に触れることで、意思決定が後押しされることもあります。
回遊率の目安は?サイトの種類によって異なる
「では、うちのサイトの回遊率は高いの?低いの?」と気になるかもしれませんが、回遊率の適切な目安は、サイトの種類や目的によって大きく異なります。
例えば、特定の情報を検索して1ページで目的が完結するQ&Aサイトや辞書サイトのような場合、回遊率は低くても問題ありません。むしろ、低い方がユーザーの利便性が高いと言えます。
一方、ECサイトや情報メディア、企業のサービスサイトなど、ユーザーに複数のページを見てもらい、商品比較や深い情報収集、ブランド理解などを促したいサイトの場合は、ある程度の回遊率(例えば、2ページ以上など)を目指すのが一般的です。
自社サイトの目的や特性を考慮し、同業種の平均値などを参考にしながら、目標とする回遊率を設定することが大切です。
なぜ低い?サイト内回遊が進まない主な原因
ユーザーがサイト内をあまり回遊してくれない場合、そこには何らかの原因が潜んでいるはずです。主な原因を見ていきましょう。
原因1:次に何をすればいいか分からない(導線が不親切)
ページを読み終えたユーザーが、「次に関連する情報はこちら」「他の〇〇も見る」といった次のアクションへの導線(案内)が分かりにくかったり、設置されていなかったりすると、ユーザーはそこで行動を終えて離脱してしまいます。
原因2:他のページに興味を持てない(関連性が低い、魅力がない)
表示されている内部リンクや関連記事が、ユーザーが今見ているコンテンツや興味関心と関連性が低い場合、クリックされる可能性は低くなります。また、リンク先のページのタイトルなどが魅力的でない場合も同様です。
原因3:欲しい情報が見つからない(ナビゲーション、検索性が悪い)
サイト全体の構造が分かりにくかったり、グローバルナビゲーション(サイト上部のメニュー)に必要な項目がなかったり、サイト内検索機能の精度が低かったりすると、ユーザーは目的の情報にたどり着けず、探すのを諦めて離脱してしまいます。
原因4:ページの表示速度が遅い
ページの読み込みに時間がかかると、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱してしまいます。特にモバイル環境では表示速度が重要視されます。次のページへ移動する際の表示速度も、回遊行動に影響します。
原因5:コンテンツの質が低い
そもそも、ユーザーが訪れたページのコンテンツ自体に価値を感じなければ、他のページを見ようという意欲は湧きません。情報の正確性、網羅性、独自性、読みやすさなど、コンテンツの質そのものが低い可能性も考えられます。
【実践編】Webサイトの回遊率を上げる効果的な施策8選
では、具体的に回遊率を上げるためには、どのようなサイト内回遊 施策が効果的なのでしょうか?代表的な8つの方法をご紹介します。
施策1:内部リンクを最適化する
内部リンクとは、自社サイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。記事の本文中に関連性の高い別ページへのリンクを設置したり、「あわせて読みたい」といった形で文末に関連記事リストを表示したりすることで、ユーザーを自然に次のページへ誘導します。
内部リンクを最適化する上では、単にリンクを貼るだけでなく、アンカーテキスト(リンクの文字列)を工夫し、リンク先のページ内容が具体的に分かるようにすることが重要です。「詳しくはこちら」だけでなく、「〇〇の機能についてはこちら」のように記述します。
例:ログリーの公式ページについてはこちら
施策2:関連コンテンツ・おすすめ記事を表示する
多くのブログやメディアサイトで見られるように、記事の最後やサイドバーなどに「関連記事」「おすすめ記事」「よく読まれている記事」などを表示するのも非常に効果的です。ユーザーの興味関心に近いコンテンツを提示することで、クリックを促し、サイト内での滞在時間を延ばします。手動で設定するだけでなく、ツールを使って自動で表示することも可能です。
施策3:パンくずリストを設置する
パンくずリストとは、「TOP > カテゴリ > 記事ページ」のように、ユーザーがサイト内のどの階層にいるのかを示すナビゲーションのことです。ユーザーは現在地を把握しやすくなり、上位のカテゴリページなどへ容易に戻ることができるため、サイト内を迷わず移動しやすくなります。
施策4:グローバルナビゲーションを見直す
サイトの全てのページに共通して表示される主要なメニュー(グローバルナビゲーション)は、ユーザーがサイト全体の構造を理解し、目的のページへアクセスするための重要な案内役です。主要なコンテンツカテゴリが網羅されているか、分かりやすい言葉で分類されているか、階層構造は適切かなどを見直しましょう。
施策5:サイト内検索機能を改善する
ユーザーが特定の情報を探している場合、サイト内検索機能は非常に重要です。検索窓を目立つ場所に設置するのはもちろん、検索精度を高めたり、入力途中で候補を表示するサジェスト機能を導入したりすることで、ユーザーが目的の情報を見つけやすくなり、サイトからの離脱を防ぎます。
施策6:ページの表示速度を改善する
ページの表示速度は、ユーザー体験に直結する重要な要素です。画像のファイルサイズを圧縮する、不要なスクリプトを削除する、サーバーの応答速度を改善するなど、表示速度を高速化するための施策を行いましょう。GoogleのPageSpeed Insightsなどのツールで現状を確認できます。
施策7:コンテンツの質を高め、続きを読みたくさせる工夫
根本的な対策として、個々のコンテンツの質を高めることが欠かせません。ユーザーの検索意図に応える有益な情報を提供するのはもちろん、魅力的な見出しをつけたり、導入文で続きを読むメリットを提示したり、適度な文字装飾や画像で飽きさせない工夫をしたりすることも、回遊率向上に繋がります。
施策8:離脱防止ポップアップを活用する
ユーザーがページを閉じようとしたり、ブラウザの「戻る」ボタンを押そうとしたりするタイミングで、ポップアップを表示して関連情報やお得なオファー(クーポン、資料ダウンロードなど)を提示する手法です。うまく活用すれば、離脱を防ぎ、サイト内回遊やコンバージョンに繋げることができます。ただし、表示頻度や内容によってはユーザーに不快感を与える可能性もあるため、慎重な設計が必要です。
回遊率改善のための分析とPDCA
これらの施策を実行する際には、必ず効果測定を行い、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
Google Analyticsでの現状把握
まずはGoogle Analytics (GA4) などのアクセス解析ツールを使って、現状の回遊率(ページ/セッション)、各ページの離脱率、ユーザーがどのようなページ遷移をしているか(経路分析)などを把握しましょう。特に離脱率の高いページや、想定通りに回遊が進んでいない箇所を特定します。
ヒートマップツールでのユーザー行動分析
ヒートマップツールを使えば、ユーザーがページのどこをよく見ているか、どこまでスクロールしているか、どこをクリックしているかなどを視覚的に分析できます。内部リンクやCTAボタンが意図通りに認識・クリックされているかなどを確認するのに役立ちます。
施策実行後の効果測定と改善の継続
改善施策を実行したら、一定期間後に再度データを測定し、施策の効果(回遊率や離脱率の変化など)を確認します。効果が見られた施策は継続・横展開し、効果が見られなかった施策は原因を分析して改善策を練り直します。この分析と改善のサイクルを地道に続けることが、回遊率向上への着実な道筋となります。
まとめ:魅力的なサイト内回遊でユーザー満足度と成果を高めよう
今回は、Webサイトの回遊率を上げるための考え方、原因分析、そして具体的な改善施策について解説しました。特に、内部リンクの最適化や関連コンテンツの表示は、多くのサイトで取り組みやすい有効な手段です。
ユーザーがサイト内をスムーズに、そして興味を持って巡ってくれるようになれば、それはユーザー満足度の向上に繋がり、ひいてはコンバージョン率の向上やブランドへの信頼感醸成にも貢献します。
紹介した施策の中から、まずは自社サイトの課題に合ったもの、取り組みやすいものから始めてみてはいかがでしょうか。そして、必ず効果測定を行い、データに基づいて改善を続けていくことが重要です。
Webサイトの回遊率を改善するには、まず現状のユーザー行動を正確に把握することが不可欠です。『Audience Analytics』のようなアクセス解析・DMPツールを使えば、どのページで離脱が多いのか、ユーザーがどのような経路を辿っているのかを詳細に分析できます。そして、分析結果に基づいて具体的な改善施策を行う際には、『Engage』のようなツールが役立ちます。Engageは、関連コンテンツのレコメンド表示や、離脱しようとしているユーザーへのポップアップ表示などを通じて、効果的にサイト内回遊を促進し、ユーザーエンゲージメントを高めることができます。データ分析から施策実行までを一貫して行い、回遊率改善に取り組みたい方は、ぜひ詳細をご覧ください。

