UGCマーケティングとは?効果的な活用方法と成功事例を徹底解説!
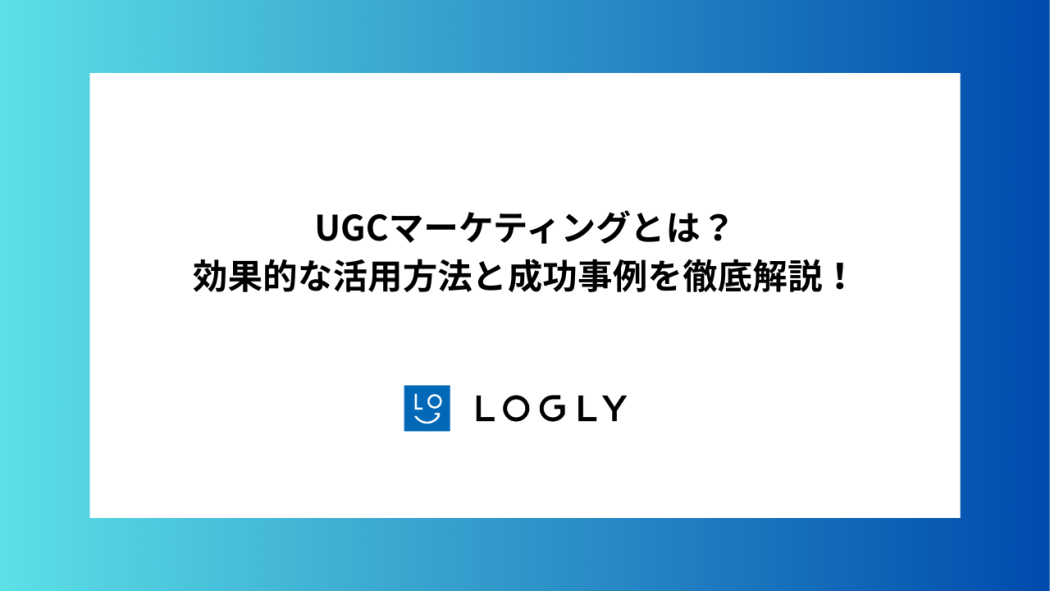
「お客様のリアルな声をもっとマーケティングに活かせないだろうか?」
「SNSで自社の商品について投稿してくれている人がいるけど、どう活用すればいいの?」
「広告っぽくない、もっと自然な形で商品の魅力を伝えたい…」
企業のマーケティング担当者であれば、このように「ユーザーの声」の重要性を感じつつも、その具体的な活用方法に悩むことがあるかもしれません。そんな中で、近年ますます注目度を高めているのが「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」を活用したマーケティングです。
この記事では、「UGCとは何か?」という基本的な定義から、その重要性、具体的な活用方法、そして成功した事例まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、UGCの力を最大限に引き出し、顧客との信頼関係を深め、マーケティング効果を高めるためのヒントが得られるはずです。
目次
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは?【基本を理解する】
UGCの定義:一般ユーザーによって作成・発信されるコンテンツ
UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)とは、企業ではなく、一般のユーザー(消費者)によって作成・生成され、主にSNSやブログ、レビューサイト、口コミサイトなどに投稿・発信されるコンテンツの総称です。
企業が発信する情報(広告や公式サイトの情報)とは異なり、ユーザー自身のリアルな体験や感想に基づいているため、他の消費者にとって信頼性の高い情報源と見なされる傾向があります。
UGCの主な種類
UGCには様々な形態があります。代表的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
SNSへの投稿:
Instagram: 商品の写真や使用感のレビュー、コーディネート投稿など
X(旧Twitter): 商品やサービスに関するリアルタイムな感想、口コミ、意見など
TikTok: 商品を使ったショート動画、チャレンジ企画への参加動画など
YouTube: 詳細な商品レビュー動画、開封動画、Vlogなど
レビューサイト・口コミサイトへの投稿:
ECサイトの商品レビュー、レストランの口コミ、旅行サイトの体験談など
ブログ記事:
個人のブログでの商品紹介記事、比較記事、体験レポートなど
Q&Aサイトへの投稿:
Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでの商品に関する質問や回答
その他:
電子掲示板への書き込み、ファンコミュニティでの発言など
なぜ今、UGCがマーケティングで重要視されるのか?
UGCが現代のマーケティングにおいて非常に重要視されている背景には、以下のような理由があります。
1. 広告不信とリアルな情報への信頼: 従来の企業からの一方的な広告メッセージに対する消費者の警戒心が高まり、より「リアルな」「自分に近い」一般ユーザーの声や体験談を信頼する傾向が強まっています。
2. 共感と購買行動への影響力: ユーザーは、同じような立場や価値観を持つ他のユーザーの意見に共感しやすく、その情報が購買意思決定に大きな影響を与えるようになっています。
3. SNSの普及による情報拡散力: スマートフォンやSNSの普及により、個人が情報を手軽に発信・共有できるようになり、UGCが瞬時に広範囲へ拡散する可能性が高まりました。
4. コンテンツマーケティングとの親和性: 企業が発信するコンテンツだけでなく、ユーザー自身が生成するコンテンツも、顧客エンゲージメントを高める上で非常に有効です。
UGCマーケティングの主なメリット
UGCをマーケティングに活用することで、企業は多くのメリットを得ることができます。
メリット1:高い信頼性と共感性を獲得しやすい
UGCは、企業ではなく一般ユーザーからの「本音」であるため、広告に比べて信頼性が高く、他のユーザーからの共感を得やすいという大きなメリットがあります。友人や知人からの口コミに近い感覚で受け止められやすいのです。
メリット2:広告感が薄く、自然な形で情報が拡散しやすい
UGCは広告特有の「売り込み感」が少ないため、ユーザーに自然な形で受け入れられやすく、SNSなどを通じて自発的に拡散される(シェアされる)可能性が高まります。これにより、オーガニックな認知拡大が期待できます。
メリット3:コンテンツ制作コストを削減できる
企業が自ら全てのマーケティングコンテンツを制作するには多大なコストと時間がかかりますが、UGCを活用することで、ユーザーが質の高いコンテンツを生成してくれるため、コンテンツ制作にかかるコストやリソースを削減できます。
メリット4:顧客エンゲージメントの向上に繋がる
ユーザーは、自分の投稿が企業に注目されたり、公式アカウントで紹介されたりすることに喜びを感じ、ブランドへの愛着や関与度(エンゲージメント)が高まる傾向があります。また、他のユーザーのUGCを見ることも、ブランドへの関心を深めるきっかけとなります。
メリット5:SEO効果も期待できる(口コミサイト等)
ECサイトの商品レビューや口コミサイトへの投稿が増えることで、Webサイトのコンテンツ量が増え、特定のキーワードでの検索順位向上に間接的に貢献する可能性があります。また、SNS上でのサイテーション(言及)もブランド認知に関わります。
【実践編】効果的なUGCを生み出すための施策
魅力的なUGCは、ただ待っているだけではなかなか生まれません。企業側から積極的にUGC創出を促すための施策が重要になります。
施策1:ハッシュタグキャンペーンの実施(SNS)
特定のハッシュタグ(例:#商品名使ってみた、#〇〇のある生活)を設定し、そのハッシュタグを付けて商品やサービスに関する投稿をしてもらうキャンペーンです。参加者の中から抽選でプレゼントを進呈するなどのインセンティブを用意することで、多くのUGCを集めることができます。
施策2:フォトコンテスト・動画コンテストの開催
テーマを設定し、商品やサービスに関連する写真や動画を募集するコンテスト形式もUGC創出に効果的です。優秀作品には賞品を用意したり、企業の公式アカウントで紹介したりすることで、参加者のモチベーションを高めます。
施策3:レビュー投稿の促進(インセンティブ設計)
ECサイトでの商品購入者やサービス利用者に対して、レビュー投稿を促す仕組みを作ります。例えば、「レビュー投稿で次回使えるクーポンプレゼント」といったインセンティブを提供することで、投稿数を増やすことができます。
施策4:商品・サービスの体験機会の提供(サンプリング、イベント)
新商品のサンプリングや、顧客を招いた体験イベントなどを実施し、その感想や体験をSNSなどに投稿してもらうよう促します。リアルな体験に基づいたUGCは、他のユーザーへの訴求力が高まります。
施策5:インフルエンサーとの連携(UGC創出のきっかけ作り)
影響力のあるインフルエンサーに商品やサービスを体験してもらい、その感想を発信してもらうことは、質の高いUGCを最初に生み出し、その後の一般ユーザーによるUGC創出の「呼び水」となる効果が期待できます。インフルエンサーのフォロワーが追随して投稿するケースも多く見られます。
施策6:コミュニティ運営によるファン育成
ブランドのファンが集まるオンラインコミュニティ(会員サイト、SNSグループなど)を運営し、その中でUGC投稿を促したり、ユーザー同士の交流を活性化させたりすることも有効です。ロイヤリティの高い顧客からのUGCは特に価値があります。
収集したUGCの具体的な活用方法
集まったUGCを、実際のマーケティング活動にどのように活用していくか、その具体的な方法を見ていきましょう。
活用法1:自社Webサイトへの掲載(お客様の声、導入事例、商品ページ)
収集したUGC(特に好意的なレビューや写真)を、ユーザーの許諾を得た上で、自社Webサイトの「お客様の声」ページや「導入事例」ページ、各商品ページなどに掲載します。これにより、サイト訪問者の購買意欲を高めたり、信頼感を醸成したりする効果が期待できます。
活用法2:公式SNSアカウントでの紹介・リポスト
ユーザーがSNSに投稿したUGCを、企業の公式アカウントで紹介(リポスト、リツイートなど)します。これにより、UGCを投稿したユーザーの満足度を高めるとともに、公式アカウントのフォロワーにもそのUGCを届けることができます。
活用法3:広告クリエイティブへの活用(SNS広告、ディスプレイ広告)
ユーザーのリアルな投稿写真やレビューコメントなどを、広告クリエイティブの一部として活用します。企業が作成した広告よりも親近感が湧き、クリック率やコンバージョン率の向上が期待できる場合があります。
活用法4:ECサイトの商品レビュー欄への掲載
ECサイトの商品ページに、購入者のレビューを積極的に掲載し、UGCを蓄積していくことは非常に重要です。星評価や具体的なコメントは、他の購入検討者の重要な判断材料となります。
活用法5:パンフレットや営業資料への活用
オンラインだけでなく、オフラインのマーケティング資料(パンフレット、会社案内、営業資料など)にも、顧客の声を引用する形でUGCを活用できます。
活用法6:商品開発やサービス改善へのフィードバックとして活用
UGCには、商品やサービスに対するユーザーの率直な意見や改善要望が含まれていることがあります。これらを真摯に受け止め、商品開発やサービス改善に活かすことで、より顧客に愛されるプロダクトを生み出すことができます。
UGCマーケティングの成功事例から学ぶ
具体的なUGCの事例を見ることで、活用イメージがより湧きやすくなるでしょう。(ここでは一般的な成功パターンを記述します。実際の事例を挙げる場合は出典に注意が必要です。)
事例1:アパレル業界のハッシュタグキャンペーン成功事例
あるアパレルブランドが、新作アイテムの発売に合わせて特定のハッシュタグを設定し、そのアイテムを使ったコーディネート写真をInstagramに投稿するよう呼びかけるキャンペーンを実施。多くのユーザーがおしゃれな着こなしを投稿し、ブランドの認知度向上と購買意欲喚起に繋がった。投稿されたUGCは公式アカウントでも紹介され、さらなる拡散を生んだ。
事例2:食品メーカーのレシピコンテスト成功事例
ある食品メーカーが、自社製品を使ったオリジナルレシピを募集するコンテストを開催。ユーザーが考案した多様なレシピがSNSやブログに投稿され、製品の新たな魅力や活用方法が広まった。入賞レシピは公式サイトで紹介され、コンテンツとしても活用された。
事例3:旅行業界のフォトコンテスト成功事例
ある旅行会社または観光地が、特定のテーマ(例:絶景、感動体験)で旅行中の写真を募集するフォトコンテストを実施。ユーザーが投稿した魅力的な写真が、その旅行先への興味関心を高め、新たな顧客獲得に繋がった。
UGC活用時の注意点と権利関係
UGCは非常に強力なマーケティング資産となり得ますが、その活用にあたってはいくつかの重要な注意点があります。特に権利関係には細心の注意が必要です。
注意点1:必ずユーザーの許諾(利用許諾)を得る(無断転載はNG)
ユーザーが作成したコンテンツ(写真、動画、文章など)には著作権があり、投稿者本人に帰属します。企業がUGCを自社のWebサイトや広告、SNSアカウントなどで二次利用する場合は、必ず事前に投稿者本人から明確な利用許諾を得る必要があります。無断で転載・利用することは著作権侵害にあたり、トラブルの原因となります。
注意点2:利用範囲や期間を明確にする
利用許諾を得る際には、「どのUGCを」「どこで(Webサイト、広告など)」「どのくらいの期間」「どのような目的で」利用するのか、その範囲を明確に合意しておくことが重要です。曖昧な許諾は、後々のトラブルに繋がりかねません。
注意点3:著作権・肖像権への配慮
UGCに投稿者以外の人物が写っている場合、その人物の肖像権にも配慮が必要です。また、キャラクターや他社の著作物などが写り込んでいる場合も注意が必要です。利用許諾を得る際に、これらの権利関係についても確認し、問題がないことを確認しましょう。
注意点4:ネガティブなUGCへの対応方法
UGCの中には、自社にとって好ましくない、ネガティブな内容のものが含まれることもあります。そのようなUGCを無理に削除したり、無視したりするのではなく、真摯に受け止め、必要に応じて丁寧に対応する姿勢が求められます。場合によっては、サービス改善の貴重なヒントとなることもあります。
注意点5:ステルスマーケティングと誤解されないための配慮(企業が関与する場合)
企業がUGC創出を促すキャンペーン(特にインセンティブを提供するもの)を実施する場合や、インフルエンサーに依頼してUGC風の投稿をしてもらう場合は、それが広告・宣伝であることを消費者に隠してはいけません(ステルスマーケティング規制に抵触する可能性があります)。「#PR」「#プロモーション」「〇〇キャンペーンに参加中」など、企業が関与していることを明確に示す表示を行うよう、ユーザーやインフルエンサーに依頼・徹底する必要があります。
まとめ:UGCの力を最大限に引き出し、マーケティングを成功に導こう
今回は、UGC(ユーザー生成コンテンツ)をマーケティングに効果的に活用するための方法や、その重要性、具体的な事例、注意点について解説しました。
企業からの一方的なメッセージよりも、一般ユーザーのリアルな声や体験談が重視される現代において、UGCは顧客との信頼関係を築き、共感を広げ、購買行動を後押しする強力な力を持っています。
UGCを戦略的に生み出し、適切に活用することで、広告効果の向上、コンテンツ制作コストの削減、顧客エンゲージメントの深化など、多くのメリットが期待できます。大切なのは、ユーザーとのコミュニケーションを楽しみ、共にブランド価値を創造していくという「共創」の視点を持つことです。
UGCを効果的に生み出し、マーケティングに活用するためには、そのきっかけ作りも重要です。特にインフルエンサーに商品やサービスを体験してもらい、その感想を発信してもらうことは、質の高いUGC創出の強力なトリガーとなります。ログリーが提供するインフルエンサーマーケティングプラットフォーム『Buzz』は、最適なインフルエンサーの選定から施策の管理、効果測定までをサポートし、UGCが自然発生しやすい環境づくりをお手伝いします。UGCの活用方法や事例を参考に、インフルエンサーマーケティングを通じてユーザーとのエンゲージメントを高めたいとお考えなら、ぜひBuzzの詳細をご覧ください。
関連プロダクト「Buzz」へのリンクはこちら

